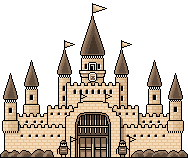<ぶらり鞍馬>
<鞍馬寺>
鞍馬寺は、宝亀元年(770年)に鑑真和上の高弟であった鑑偵上人が、
本尊として毘沙門天を奉安したことで始まるとされています。
幼名を牛若丸と呼ばれた源義経は、7歳の時に鞍馬寺に入り
およそ10年の間に東光坊に住み修行を行いました。
昭和22年(1947年)に天台宗の寺院から、新たに立教された鞍馬弘教の総本山となりました。
霊夢のお告げにより霊山を求めていた鑑偵は、
この鞍馬山の上方に宝の鞍を乗せた白馬の姿を見たため足を踏み入れたところ、
女の姿をした鬼に襲われ、殺される寸前で枯れ木が倒れて
鬼が下敷きになり潰され、難を逃れたそうです。
翌朝、その場所に毘沙門天像があったので、これを祀ったのがはじまりと言われています。

叡山電鉄の鞍馬駅前には、鞍馬に縁のある大天狗が待ち構えています。
ここは「鞍馬天狗」の名でも知られるように、天狗たちの総本山でもあります。
※久しぶりにリフレッシュできました!
|

仁王門(山門) |
明治44年の再建。
左側の扉は、 寿永の頃(1182〜4)のもの。
両側に立つ仁王尊像は運慶の嫡男、
湛慶作と伝承。浄域への結界。 |

由岐神社 |
由岐神社の祭神の「靫明神」は、
天慶三年(940)天慶の乱が起きたので
朱雀天皇の勅により、鞍馬寺に遷宮し、
北方鎮護を仰せつかった鎮守社 |

本殿金堂・金剛床 |
宇宙の大霊、尊天のお働きを象徴する
千手観音菩薩・毘沙門天王・護法魔王尊
(脇侍、役行者・遮那王尊)を奉安する中心道場。

金剛床は、宇宙のエネルギーである
尊天の波動が果てしなく広がる星曼荼羅を模したもの。 |

木の根道 |
根が地表面でアラベスク模様を描くのは、
この辺り一帯の砂岩が、
灼熱のマグマの貫入によって硬化したために
根が地下に伸びることが出来なかったため。
牛若も「木の根道」で
兵法修行をしたと伝えられています。
|

義経堂 |
奥州で非業の死を遂げた義経の御魂は、
懐かしい鞍馬山に戻り
安らかに鎮まっていると伝えられ、
遮那王尊として祀られています。 |

不動堂 |
伝教大師、最澄が天台宗立教の悲願に燃え、
一刀三礼を尽くし刻んだ不動明王が奉安されています。
少年時代の源義経、
牛若丸が鞍馬天狗に
兵法を教わった場所と言われます。 |

魔王殿 |
奥の院、魔王殿は、
650万年前に金星から護法魔王尊が
地球に降り立った場所とされています。
鞍馬山鞍馬寺は、きわめてパワーの強い場所です。
それも「魔王尊」という字の通り、
「魔を封じ込めている」とも言われます。 |